最新情報
『最新 建物移転補償実務-今日的課題を中心として-』の刊行
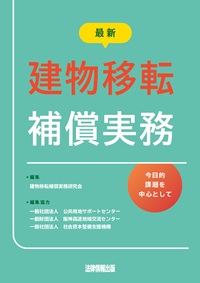
建物の移転工法については、平成元年に従来の既存建物を解体し移築するという代表的な工法が抜本的に見直されましたが、その後三十数年経過した現在も、社会経済情勢の変化を踏まえ、部分的運用見直しがなされて今に至っています。
そこで、平成元年の見直しの経緯を振り返りながら、実務上の運用の移り変わりを整理して、今後の実務に役立ててもらうことを目的として本書を発刊しました。
具体的には、第1部で「建物移転補償の見直し箇所」を抽出して背景説明や解説を加え、第2部では「建物移転補償の今日的課題」として、①用地取得において、多数当事者を相手として建物の所有及び利用関係について規定している「建物の区分所有等に関する法律」が優先的に適用されるマンション等区分所有建物についての取扱い及び、②「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」で創設された「配偶者居住権」が設定された建物に対する補償の基本的な考え方等今後の移転補償実務において必須となる情報について解説しています。
『窓口担当者のための「内部通報制度」の実務~運用における留意点と実例解説~』を発刊

令和4年6月1日から施行された改正公益通報者保護法(以下「改正法」)は、事業者等に対して、①公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正法11条1項)、内部公益通報対応体制の整備その他必要な措置をとる義務(同条2項)、従事者等に対する公益通報者を特定させる情報に関する守秘義務(同法12条)という3つの義務が課されることになった。
そこで、「事業者等の義務」についての理解を助けるため「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年8月20日内閣府告示第118 号)及び「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」を制定・公表するなどして、内部通報を積極的に活用することにより不祥事の早期発見や是正を行うための事業者自らのより積極的な取組みを促している。
本書では、改正法で規定された事業者等の義務の具体的な実務対応として内部通報制度を機能させていくための制度構築、運用面を通じて検討すべき諸要素について、直近までの裁判例・20件の分析等も紹介しながら、内部通報に携わる弁護士、企業内弁護士の視点から解説している。
「労働事件関連」の待望の2冊、改訂なる。
かねてより改訂作業を続けていた東京弁護士会労働法制特別委員会編集の待望の2冊が発刊となりました。
![(改訂版)入門 労働事件[解雇・残業代・団交・労災]=新人弁護士 司君ジョブトレ中=の表紙](common/img/book/202103_roudoujiken_kaitei.jpg)
『(改訂版)入門 労働事件[解雇・残業代・団交・労災]=新人弁護士 司君ジョブトレ中=』
平成25年2月初版発行以来7年が経ち、この間に雇用環境をとりまく情勢は激変し、労働事件の全民事事件に占める比重の高まりとともに、多くの弁護士が「労働事件」に積極的にチャレンジするようになりました。同時に、本書初版を執筆した「若手部会メンバー」も委員会活動の中心的役割を担うようになり、今回改訂では、近時の法改正に対応したのはもちろんのこと、各執筆者のこの間の研鑽や経験の成果が各所に反映されています。
「第1部 個別的労働関係紛争」では代表的な事件類型である「解雇、割増賃金請求(残業代)」を、「第2部 集団的労働関係紛争」では「団交」を、「第3部 労働災害」では「労災」を取り上げ、<新人弁護士 司君>の日々の活動を通じた<ストーリー仕立て>により、労働事件で直面する典型的な問題について、各場面での留意点や必要となる諸手続・各種書証の作成等、実践的な知識を幅広く、分りやすく解説しています。

『ケーススタディ労働審判(第3版)』
平成18年4月1日から始まった労働審判手続は、個別的労働紛争の適切かつ迅速な解決方法として高い評価をうけるとともに活発に利用されており、事案の性質による労働審判利用の可否の検討及びその具体的な運用に精通することは、労働事件を扱う弁護士や関係者にとって必須の知識となっています。労働法制特別委員会では、労働者側、使用者側、双方を担当する多数の弁護士が参画して活発な議論を重ねており、第3版では、最近の法改正動向や運用状況とともに、前回改訂からここまでの研究や労働審判実務での成果を取り入れてさらに充実させました。
本書は、第1部で「早わかり労働審判」として最近の労働審判手続の運用状況等を概観し、「第2部 事件の相談・受任から解決まで」では、弁護士への相談~当事者双方からの申立書・答弁書等書証の作成・提出~原則3回とされる労働審判廷での審尋例(審判官・審判員・代理人・本人によるやりとり)~事件の解決までの詳細を時系列でまとめ、「第3部 主要紛争類型のポイント」では相談から解決までのエッセンスを解説しました。
