『最新 建物移転補償実務-今日的課題を中心として-』(「はじめに」より抜粋)
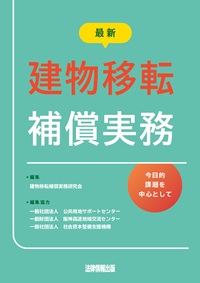
建物の移転工法については、平成元年に従来の既存建物を解体し移築するという代表的な工法が抜本的に見直されました。
そして、その後三十数年経過した現在も、社会経済情勢の変化を踏まえ、部分的運用見直しがなされて今に至っています。
そこで、平成元年の見直しの経緯を振り返りながら、実務上の運用の移り変わりを整理して、今後の実務に役立ててもらうことを目的として本書を発刊しました。
具体的には、「第1部」において建物等の移転補償の基本的な考え方について解説しました。すなわち、公共事業のために通常必要とされるのは土地であり、その土地に存する建物等は一般的には事業に必要とされないことから、建物等の補償における基本原則は、建物を起業地外に移転することが大前提となるからです。
続く「第2部」では、<建物移転補償の今日的課題>として、①用地取得において、多数当事者を相手として建物の所有及び利用関係について規定している「建物の区分所有等に関する法律」が優先的に適用されるマンション等区分所有建物についての取扱い及び、②「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号、令和2年4月1日施行)で創設された「配偶者居住権」が設定された建物に対する補償の基本的な考え方等、今後の移転補償実務において必須となる情報について解説しています。
【目次】
|
目 次 はしがき 第1部 建物移転補償の実務(基礎編) 1│移転補償の基本的な考え方 (1)建物移転主義の原則 ⇒ 移転主義 (2)精神的補償はしない (3)合理的な移転先の認定 ① 有形的検討 ② 機能的検討 ③ 法制的検討 ④ 経済的検討 2│移転工法の種類 (1)復元工法 |
(2)除却工法 (3)曳家工法 (4)改造工法 (5)再築工法 ① 構内再築 【照応建物とは】 ② 構外再築 3│法令等の位置づけ (1)土地収用法 (2)土地収用法第88条の2の細目等を定める政令 (3)公共用地の取得に伴う損失補償基準 (4)公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 |
Q&A
Q1 平成元年の移転工法改正の背景と経緯について教えてください。
Q2「残地」が合理的な移転先となるかどうかを検討する場合の「経済的検討」の意義はどこにあるのでしょうか。
Q3「残地」が合理的な移転先となるかどうかを検討するにあたり、有形的検討・機能的検討・法制的検討をした結果、合理的と判断されたときは、構外の再築工法による補償総額を超えてもよいのでしょうか。
Q4 改造工法の認定にあたっての留意事項はどのような点ですか。
Q5 既存不適格の建物について、法令上の施設改善費用の取扱いはどうしたらよいですか。
Q6 再築補償率の補正をする場合、それぞれの補正項目の確認及び補正率の判断基準はどう行ったらいいのでしょうか。
Q7 再築補償率の補正は、建物の経過年数に関係なく適用してよいのでしょうか。
Q8 非木造建物についても、木造建物に準じて再築補償率における耐用年数を補正することができるのでしょうか。
Q9 復元工法は「文化財保護法等により指定された建築物」を対象としているが、土地区画整理事業施行区域内の建築物についても対象となるでしょうか。また「文化財保護法等」の「等」にはどのようなものがあるのでしょうか。
Q10 構内の再築工法において、借家人に対する補償が、仮住居補償によらず借家人補償によることができるとしたのはなぜでしょうか。
Q11 構外の再築工法において、2か月の範囲内で相当と認める期間、営業休止補償を認めるのはなぜでしょうか。
Q12 補償基準細則第28において、従来の「移転後の経営効率を大きく低下させることとなる場合は、全部移転による補償額を検討して本条の適用を行なうものとする」を削除したのはなぜでしょうか。
Q13 工作物の移転料を算定する場合において、建物に付随する工作物を除いた工作物はすべて復元工法によるべきでしょうか。
Q14 移転先の検討にあたり、相手方が残地に隣接する農地を移転先として申し出ている場合、これを含むことが可能ですか。また、高低差を解消するための盛土造成工事が必要な場合、これを補償することは可能ですか。
Q15 違反建築物については、移転補償上において、どのように扱えばよいですか。
第2部 建物移転補償の今日的課題(応用編)
1│区分所有建物(マンション)
(1)区分所有建物とその敷地の法的性格
① 建物
1)専有部分
2)共用部分
② 敷地
③ 分離処分の制限
④ 規約の設定等
⑤ 管理組合
(2)区分所有建物敷地の補償の基本的な考え方
(3)区分所有建物の移転及び取得補償
① 建物敷地の一部が計画線にかかる場合
② 建物の一部が支障となる場合(区分所有建物の共用部分が計画線にかかった場合)
③ 建物の一部(または全部)が支障となる場合(区分所有建物の専用部分が計画線にかかった場合)
(4)区分所有権等の取得補償の意義
(5)区分所有権等の算定
① 敷地利用権の価格
- 基本用語解説
区分所有権/敷地利用権/敷地権 - 注釈
正常な取引価格による価額/減価補正/共有持分の割合
② 区分所有権の取得価格(実施要領第8条)
③ 取引事例比較法による比準価格(実施要領第9条)
- 注釈
区分所有権等/基準戸
【区分所有権等の比準価格算定の具体的な流れ(比較の方法)】
④ 原価法による区分所有権等の積算価格(実施要領第10条)
- 注釈
原価法/効用比による配分率/建物及び敷地の再調達原価に係る減価
修正/建付地としての減価補正
(6)区分所有建物敷地取得に係る補償手続
【敷地利用権の売却手続】
(7)残存区分所有者の事業用地内に存する敷地利用権との交換(実施要領第7条)
(8)建物の一部が支障となる場合に取得する建物の範囲(実施要領第12条)
(9)区分所有建物の一部切り取り可能な場合の残存区分所有建物に対する補償(実施要領第13~17条)
(10)法令等の位置づけ
【土地収用法】
【補償基準】
【区分所有建物敷地取得補償実施要領】
Q&A
Q1 区分所有権を取得しない場合の敷地の評価はどのように考えたらよいでしょうか。
Q2 区分所有権等の価格を取引事例価格から算定する場合、どのような事例を収集することがよいでしょうか。
Q3 各戸の区分所有権等の評価にあたり、販売会社が設定した販売価格表を参考として算定することは妥当でしょうか。
Q4 区分所有者の総意で残地にほぼ従前と同規模の区分所有建物を再築したいとの要求がある場合、残地を特定移転先として移転補償を認定することは妥当でしょうか。
Q5 マンション建替法を活用した補償方法にあたり、どのような点に留意すべきでしょうか。
Q6 区分所有建物敷地の一部取得に伴いコンクリート叩き等の附帯工作物が支障となりますが、残地内に移転する場所も移転する必要もないと判断される場合の補償方法、移転料算定としては、どのように扱ったらよいですか。
Q7 駐車場が支障となり、敷地内に移転場所が確保できない場合の駐車場利用者の駐車場が利用できないことに対する補償はどのように扱ったらよいですか。
Q8 建物は支障とならず、区分所有建物敷地の一部を取得するケースにあたり、管理組合等において総会の決議を経る必要がある事項として、具体的にどのようなものが挙げられるのでしょうか。
Q9-① 区分所有建物敷地の一部を取得することになりますが、取得部分の分筆登記手続につき、近年要件緩和がなされたようですが、どのような扱いとなりますか。
Column ●被災地における用地取得補償の取扱方針
Q9-② 区分所有建物敷地の一部を取得することになりますが、登記手続に関して、具体的にどのようなものが必要となりますか。
Q10 土地収用法における未取得の区分所有権の収用はどうすればいいですか。
2│配偶者居住権を有する者に対する建物移転補償
(1)はじめに
(2)配偶者居住権の概要
① 趣旨
② 改正前後の比較
1)改正前
2)改正後
③ 配偶者居住権の設定登記件数等
④ 権利の内容
1)成立要件
2)性質
3)存続期間
4)権利の始期
5)権利の消滅
⑤ 配偶者短期居住権の概要
1)法的性質
(3)補償の基本的な考え方
① 前提となる各種制度趣旨
【配偶者居住権の評価の考え方】
【敷地利用権の評価の考え方】
② 配偶者居住権等に関する補償の基本方針
1)建物
2)土地
3)その他
③ 配偶者短期居住権に対する補償方針
④ 配偶者居住権に関する補償基準の構成
⑤ 配偶者居住権の目的となっている建物の移転に係る補償(控除方式)具体の算定例
⑥ 配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供されている土地に対する補償具体の算定例
⑦ 配偶者居住権が消滅する場合の移転工法
(4)法令等の位置づけ
【土地収用法】
【補償基準】
【配偶者居住権補償実施要領】
- 注釈
使用・収益/債権
Q&A
Q1 配偶者居住権者と借家人とにおいて、補償の取り扱いに違いがあるのはなぜですか。
Q2 建物の共有者兼配偶者居住権者となる場合の補償額算定上の取り扱いはどのようになりますか。
Q3 敷地の一部が事業計画内にあり、建物移転が必要な(建物が滅失する移転工法を認定している)場合における残地部分に係る配偶者居住権に基づく敷地利用権の消滅に伴う補償等はどのようになるのですか。
Q4 補償対象となっている建物が複数棟ある場合の取り扱いはどうすればいいのでしょうか。
Q5 塀や門扉など工作物のみが支障となる場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。
Q6 土地所有者と建物所有者が異なる、すなわち、借地権等が土地に設定されている場合の配偶者居住権の敷地利用権相当分の補償はどのように扱うことになりますか。
Q7 配偶者居住権の有無の調査は、どのように行うのですか。
Q8 配偶者居住権の有無の調査方法のうち、聞き取り前の公的資料調査に関して、どのような留意点が挙げられますか。
Q9 聞き取り調査等実施にあたっての留意点としては、どのようなことが挙げられますか。
Q10 配偶者居住権者に対する消費税等の税額、消費税等相当額はどのように扱われるのですか。
3│「補償基準」等改正の動向
-建物調査算定等検討の方向性-
(1)現状の課題
① 用地関係業務
② 建物の調査算定
③ 建物の市場価格等
(2)整理の方針
① 建物移転料と市場価値
② 建物の推定再建築費
③ ツー・バイ・フォー工法、プレハブ工法の建物の調査算定基準化
④ 住宅用途に係る調査積算の共通化
⑤ 補償標準単価
(3)要領の主要改正事項
① 建物の区分(木Ⅰ・非木Ⅰの拡充)
② 要領の追加(ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法)
③ 除却工法における所有者不明土地法等との整合
(参考)地域福利増進事業ガイドライン(令和4年11月国土交通省不動産・建設経済局)
(4)その他用地DXの動き
(参考)建物移転料算定要領(令和6年2月28日改正新旧)
Column ●公費解体制度とは何か。
(参考)用地行政の最近の動き
1.所有者不明土地に関する現状と課題
2.用地関係業務に係るDXの現状紹介
附録 資料編
【法令】
◎建物の区分所有等に関する法律〔抄〕
◎民法〔抄〕
(参考)●配偶者居住権と配偶者短期居住権の比較表
【通知】
- 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)(通達)〔抄〕
【裁決例】
- 道路予定地であることを認識した上で、当該地に苗木を密植した者に対し、本件植栽はもっぱら補償の増額を目的としたもので、損失補償制度の趣旨、目的に反し、信義則にも反する権利の濫用であることは明らかであるとして、補償を認めなかった事例〔抄〕
【判例】
◇法令施設改善費用に係る運用益相当額は、土地収用法88条にいう通常受ける損失に当たるとした事例(大阪高判平成6年11月29日裁判所ウェブサイト、判例タイムズ881号85頁)
参考文献等
編集協力団体一覧
『窓口担当者のための「内部通報制度」の実務~運用における留意点と実例解説~』

令和4年6月1日から施行された改正公益通報者保護法(以下「改正法」)は、事業者等に対して、①公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正法11条1項)、内部公益通報対応体制の整備その他必要な措置をとる義務(同条2項)、従事者等に対する公益通報者を特定させる情報に関する守秘義務(同法12条)という3つの義務が課されることになった。
また、行政機関等への外部通報保護要件の緩和(改正法3条2号、3号)、通報者がより保護されやすくなるよう保護対象通報者の範囲に「退職後1年以内に通報した退職者と法人役員」を加え(改正法2条1項、5条3項、6条)、通報対象事実の範囲に過料の対象となり得る行為を含め(改正法2条3項)、保護の内容として通報に伴う損害賠償責任の免除が追加された。
そこで改正法では、「事業者等の義務」について理解を助けるため「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年8月20日内閣府告示第118 号)及び「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」を制定・公表するなどして、内部通報を積極的に活用することにより不祥事の早期発見や是正を行うための事業者自らのより積極的な取組みを促している。
本書では、改正法で規定された事業者等の義務の具体的な実務対応として内部通報制度を機能させていくための制度構築、運用面を通じて検討すべき諸要素について、直近までの裁判例・20件の分析等も紹介しながら、内部通報に携わる弁護士、企業内弁護士の視点から解説している。
【目次】
|
発刊によせて はじめに 第1章 企業における内部通報制度構築の基本 [1]公益通報者保護法の概要と改正に至る経緯 ❶ 公益通報者保護法の概要 ➋ 改正に至る経緯 [2] 内部通報制度構築の観点からみる改正法のポイント ❶ 改正を検討された問題点 ❷ 改正法に反映された点 ➌ 企業における内部通報制度構築 [3] 内部通報制度構築における基本的観点 ❶ 企業における内部通報制度の位置付け ❷ 制度構築に必要な複眼的観点からの検討 第2章 内部通報制度と処理のモデル [1]はじめに [2]通報者の範囲 ❶ 通報者の範囲 ❷ 違法・不正行為を行った従業員を通報者に含める場合の対応 ➌ 想定していない通報者への対応 ❹ 社内規程例 [3]内部通報の内容・通報対象 ❶ 内部通報の内容・通報対象 ❷ 内部通報の具体例 ➌ 内部通報の対象外とされる内容 ❹ 社内規程例 [4]内部通報の受付窓口 ❶ 内部通報の受付窓口 ❷ 社内窓口 ➌ 社外窓口 ❹ 企業グループの通報窓口 ❺ 組織の長その他幹部からの独立性の確保 ❻ 通報従事者 ❼ 社内規程例 [5]内部通報の通報方法 ❶ 内部通報の通報方法 ❷ 電子メール、ウエブサイト ➌ 電話 ❹ 匿名での通報 ❺ 社内規程例 [6]内部通報受付後の対応 ❶ 内部通報受付後の対応 ❷ 通報内容の検討 ➌ 事実調査 ❹ 事実認定と評価 ❺ 是正措置・再発防止策の実施 ❻ 被通報者等に対する処分と公表 [7]通報者の保護 [8]内部通報制度の教育・周知 [9]内部通報規程の例 第3章 内部通報処理の実務 [1]はじめに [2]通報窓口担当者(公益通報対応業務従事者)の心構え ❶ 通報者の秘密保持と不利益取扱い防止が最優先 ❷ 公益通報か否かの判断は急がない ➌ 通報対応の処理(一般的な流れ) ❹ 範囲外共有等の防止 [3]通報受付業務とその留意点 ❶ 通報の受付方法 ❷ 匿名による通報への対応 ➌ 通報者の範囲(退職者からの通報) ❹ 通報受理の通知 ❺ 通報内容・調査要否の検討 ❻ 調査を実施しなくともよい場合 ❼ 調査体制・調査計画(方針)の策定 ❽ 検討結果の通知 ❾ 通報者の意に反する調査 [4]調査業務とその留意点 ❶ ポイント ❷ 物的証拠(客観的証拠)の収集 ➌ 人的証拠(主観的証拠)の収集 [5]調査結果を踏まえた是正措置と再発防止策 ❶ 是正措置及び再発防止策 |
❷ 行為者に対する懲戒処分等 [6]通報者対応とその留意点 ❶ 調査状況の通知 ❷ 対応結果等の通知 ➌ 通報対応終了後のフォローアップ ❹ 不適切な通報に対する対応 第4章 内部通報制度における弁護士の活動 [1]外部窓口担当上の注意点 ❶ 窓口担当弁護士の立場 ❷ 通報対応と守秘義務 ➌ 調査計画への助言 ❹ 不利益取扱いの予防措置 ❺ 調査結果のフィードバック ❻ 不利益取扱いに関するフォローアップ [2]外部窓口の独立性と顧問弁護士 ❶ 指針及び指針の解説 ❷ コーポレートガバナンス・コード ➌ 弁護士職務基本規程 ❹ 顧問弁護士と外部窓口の兼任 [3]窓口担当弁護士の役割 [4]調査委員会と弁護士 ❶ 外部窓口と調査委員会との異同 ❷ 2つの種類の調査委員会 ➌ 調査委員会における弁護士の役割 ❹ 公益通報と調査委員会 ❺ 顧問弁護士と調査委員会 ❻ 公益通報対応業務従事者の指定との関係 第5章 内部通報に関する重要判例の解説 重要判例解説・細目次 ※各事案とも「事案の概要」「判決(決定)の要旨」「解説」で構成 [1]Yタクシー会社(雇止め) 事件 (京都地決平成19年10月30日労判955号47頁) [2]オリンパス配転無効事件 (最一小決平成24年6月28日) [3]D大学解雇無効事件 (広島地福山支判平成17年7月20日裁判所ウェブサイト) [4]海外漁業協力財団事件 (東京高判平成16年10月14日労判885号26頁) [5]学校法人田中千代学園事件 (東京地判平成23年1月28日労判1029号59頁) [6]岩国市農業協同組合事件 (山口地岩国支判平成21年6月8日労判991号85頁) [7]学校法人北里研究所事件 (東京地判平成24年4月26日労経速2151号3頁) [8]退職従業員による取引先への告発事件 (東京地判平成19年11月21日判時1994号59頁) [9]日本プロボクシング協会事件 (最二小決平成28年6月8日) [10]千葉県がんセンター事件 (東京高判平成26年5月21日労経速2217号3頁) [11]世田谷保健所事件 (東京地判平成27年1月14日労経速2242号3頁) [12]自治労共済事件 (広島高松江支判平成25年10月23日) [13]大王製紙事件 (最二小決平成29年6月28日) [14]武生信用金庫事件 (名古屋高金沢支判平成28年9月14日労判ジャーナル57号23頁) [15]学校法人常葉学園事件 (最二小決平成30年1月19日) [16]イビデン事件 (最一小判平成30年2月15日労判1181号5頁) [17]学校法人國士舘ほか事件 (東京高判令和3年7月28日) [18]京都市事件 (大阪高判令和2年6月19日労判1230号56頁) [19]海外需要開拓支援機構ほか事件 (東京地判令和2年3月3日労判1242号72頁) [20]福岡県筑前東部地区連絡会事件 (福岡地判令和3年10月22日) 編集・執筆者略歴 |
『(改訂版)入門 労働事件[解雇・残業代・団交・労災]』
![(改訂版)入門 労働事件[解雇・残業代・団交・労災]=新人弁護士 司君ジョブトレ中=の表紙](common/img/book/202103_roudoujiken_kaitei.jpg)
『(改訂版)入門 労働事件[解雇・残業代・団交・労災]=新人弁護士 司君ジョブトレ中=』発刊にあたって本書の初版以来、7年を経過致しましたが、この間、雇用環境をとりまく情勢は激変し、労働事件の全民事事件に占める比重は益々重くなってきており、従前と異なり、多くの弁護士が積極的に労働事件にチャレンジするようになっています。
また、編集を担当した東京弁護士会労働法制特別委員会は、現在、中堅・ベテランも含め130名を超える労使双方の弁護士が参加し、本委員会開催の際に毎回行われる外部講師を招いての研究会等で「同一労働同一賃金」などに関する研究を重ねてきたほか、近時提起されている様々な問題に対応すべく、「判例研究部会」「法教育部会」「公務員労働法制研究部会」「企業集団/再編と労働法部会」において活発な活動を行っています。
このような中、本書初版を執筆した「若手部会」メンバーも前記各部会等の中心的役割を担うようになっており、この「改訂版」では、近時の法改正に対応したのはもちろんのこと、各執筆者の労働問題に関する研鑽や経験の成果が各所にちりばめられたものとなっています。
本書の構成
「第1部 個別的労働関係紛争」では、代表的な事件類型である「解雇」と「割増賃金請求[残業代]」を取り上げ、「解雇」では労働局のあっせんと労働審判について必要な知識が、「割増賃金請求[残業代]」では手続の選択や訴訟で問題となる必要な知識が、幅広く、それでいてポイントをついて簡潔に分かりやすくまとめられています。「第2部 集団的労働関係紛争」、「第3部 労働災害」においても、労働事件で直面する典型的な問題について、実践的な知識が記載されています。
また、本書は「新人弁護士 司君」の日々の活動を通じた<ストーリー仕立て>として読みやすい体裁となっていますが、その実は、本委員会において研鑽を積みながら労働事件を担当している弁護士が議論を重ね、事件を担当するにおいて必要なことを記載したきわめて実践的な労働事件の入門書となっています。
『ケーススタディ 労働審判(第3版)』

『ケーススタディ 労働審判(第3版)』発刊にあたって
労働審判制度は、平成18年4月1日の労働審判法施行以来、最も成功した司法制度改革として高い評価を得て活発に利用されており、事案の性質による労働審判利用の可否の検討及びその具体的運用に精通することは、労働事件を扱う弁護士や関係者の皆様にとって必須となっています。
また、本書編集を担当した東京弁護士会労働法制特別委員会には、労働者側・使用者側・労使双方を担当する130名を超える弁護士が参加して、この労働審判制度を含め活発な議論を重ねており、この(第3版)では、最近の運用状況による加筆訂正のほか、(改訂版)からこれまでの研究の成果を漏らすことなく取り入れ、改訂を加えました。
本書の構成
「「第1部 早わかり労働審判」では、労働審判制度を利用するにあたっての事案ごとの必要な情報とノウハウをまとめ、「第2部 事件の相談・受任から解決まで」では、「普通解雇」(労働者側申立て)、「社内組織の再編と降格・配転」(労働者側申立て)、「債務不存在確認(退職理由と退職金の不支給)」(使用者側申立て)、「割増賃金の請求」(労働者側申立て)の4つのケースについて、弁護士への相談~双方代理人による申立書・答弁書等書証の作成・提出~原則3回にわたる審判廷での審尋(審判官・員、代理人、当事者のやりとりの詳細)~事件の解決までを時系列でまとめ、「第3部 主要紛争類型のポイント」では、「懲戒解雇の無効」(労働者側申立て)、「整理解雇(変更解約告知)の無効」(労働者側申立て)、「雇止めの無効」(労働者側申立て)、「退職金債務不存在確認(競業避止義務違反)」(使用者側申立て)、「パワハラ損害賠償請求」(労働者側申立て)の5つのケースについて、相談から解決までのエッセンスを解説しています。
大学テキスト採用書籍(2025年)
◎十文字学園女子大学 教授・片居木 英人 先生
社会情報デザイン学部 社会情報デザイン学科(他学科解放科目)、2年生後期(半年)
『現代社会と人権-「共生」を考えるための15講-』

本書の特徴
「2001年から21世紀がスタートしました。そして、今日、その5分の1が経過しています。しかし、ここで、とくに強調しておきたい点は、戦後<1945年以降>、私たち人間社会(人類社会)は、はたして、どれだけの人権問題を解決しえてきたのか、ということです。地球社会上の全生命にとっての、新たなる壮大な“脅威”も、立ち現れてきています。こうした厳しい状況にしっかりと向きあい、解決への社会的努力の成果を着実に積み重ねていくことが、つよく求められています。
「共生(ともに生きること)」の実現のためには、専門・分化という“縦割り"
を超えるという視点が、ぜひとも、必要です。総合性・連携性・多様性という包摂的な-横断的な-認識方法が欠かせません。また、「~者問題」として対象を限定してしまうと、その枠に当てはならない、取りこぼしてしまう人々(存在)を生み出してしまう危険性もあります。人権問題は、この<選別の>危険性に十分に注意を払う必要があります。
本書も〔この試みに〕どれだけ成功したかは、はなはだ疑問です。しかし、横断的な認識方法をもって、「~者福祉」からの脱却という問題意識をもって、全体および各講の展開を試みたつもり」であり、「「共生」を考えるための15講が、また、「現代社会と人権を考えるための一助となっていることを願ってい」るとの筆者「あとがき」の文言が、この本の<ねらい>を語りつくしているように思います。
【目次】
|
はじめに 第1講 日本国憲法を基軸にして
第2講 男女共同参画と人権①-ジェンダーを問う
第3講 男女共同参画と人権②-人権としての「平等・発展・平和」
第4講 セクシュアリティと人権①-多様なセクシュアリティのかたち
第5講 セクシュアリティと人権②-基本的人権としての性的人格権
第6講 子ども虐待と人権-「人権・権利・人権擁護」、「親権」の意味を考える
第7講 「障がい」と人権①-「障がい」とは、なにか
第8講 「障がい」と人権②-障害者の権利条約、障害者差別解消法の視点から
|
第9講 ハンセン病と人権-なぜ、「隔離」や「断種」は、つづけられたのか
第10講 「高齢期」と人権-「人間の安全保全」という視点から
第11講 「自立」と人権-福祉において「自立」が強調されると…
第12講 「異国籍」と人権-「国籍のちがいを理由とした差別」問題
第13講 「食事」と人権-飢餓と、「食品廃棄」と…
第14講 動物の権利-「動物愛護」を超えて
第15講 AIロボットの権利-その権利は、認められるか
おわりに |
◎十文字学園女子大学 教授・片居木 英人 先生
教育人文学部、幼児教育学科、1年生前・後期(半年)
◎十文字学園女子大学 講師・安達 宏之 先生
人間生活学部、教育人文学部、社会情報デザイン学部、1年生前・後期(半年)
『【改訂新版】日本国憲法へのとびら(2訂)-いま、主権者に求められること-』

本書の特徴
「はじめに~憲法を学ぶことの意味~」によれば、本書の狙いを著者は次のように語っています。
そんな大切な、選挙権をもつ主権者となるあなたへ、日本国憲法からメッセージを贈りたいのです。主権者として是非知っておいてほしい憲法のこと、人権のこと、平和のこと、政治の仕組みのこと、まだまだたくさんあります。それらが各章からやさしく、ときに"鋭く"届けられます。どうぞ、そのそれぞれのメッセージを受けとめていただき、日本国憲法の理解の上に立った、真の「主権者」となっていただきたいと願っています。
今回、【改訂新版】としてリニューアルする当たり、より読みやすくするため各章に「小見出し」をつけました。
また、従前までは「補章 原発事故・放射能問題と憲法の精神」としていたものを、新たに「第5章 日本国憲法の精神と環境権」として本書の憲法(人権保障)体系論に組み込み、さらに他章についても必要最小限の加筆・修正を行いました。
とはいえ、小林直樹先生の『憲法を読む』と同じ思いから出発するところからは変わることなく、ここでまた改めて私たちの『【改訂新版】日本国憲法へのとびら-いま、主権者に求められること-』の「とびら」を開いていくことにいたします。成人を迎える大学生や広く一般読者に向けて、「日本国憲法からのメッセージ」をやさしく・分かりやすく解説しました。
第1章 憲法とは何か/第2章 日本国憲法はこうして生まれた/第3章 日本国憲法の基本原理/第4章 基本的人権の種類と内容/第5章 日本国憲法の精神と環境権/第6章 日本国憲法がめざす平和主義/第7章 国民主権とは/第8章 国家権力の分立/第9章 国会のしくみとはたらき/第10章 内閣のしくみとはたらき/第11章 裁判所のしくみとはたらき/第12章 財政と租税(税金)/第13章 地方自治とは/第14章 憲法保障と憲法改正/第15章 「平等・発展・平和」と日本国憲法
◎十文字学園女子大学 講師・安達 宏之 先生
人間生活学部、教育人文学部、社会情報デザイン学部、1年生前・後期(半年)
『生物多様性と倫理、社会-改訂版-』

本書「はじめに」によれば、著者の<テーマ設定>や<ねらい>及び<論点等>は次のとおりです。
「生物多様性」という用語は、自然環境の保全を考える際に必ず登場するものではあるが、古くから使われていた用語ではなく、1992年の「地球サミット(国連環境開発会議)」やその年に採択された「生物多様性条約」によって世界中に一気に広まったものであり、その歴史はわずか三十有余年といえます。そうした事情も影響してか、「生物多様性」について語られることが多くなったものの、その意味を正確に理解している人は決して多くはないようです。
本書では、こうした<生物多様性の意味や意義>について考えていきます。生命が誕生して40億年、現在は6回目の大量絶滅時代と言われていますが、それを引き起こしているのは「私たち人類」であり、この危機の深刻さを認識するためにも<生物多様性への正しい理解>が求められているのです。
本書は、書名が示すとおり「生物多様性と倫理、社会」をテーマとしていますが、単に<生物多様性そのものの解説>にとどまることなく、「生物多様性」に関する「倫理」や「社会」のあり方について考えていきます。そもそも「生物多様性」を考える上で、生命に関する難しい問題も横たわっています。例えば、「人と他の生物の区別はつくか?」という問いに、説得力のある答えを出すことができるでしょうか。また、保全すべき対象である「自然」とはどのようなものでしょうか。人が立ち入ることがない原生自然のみが保全の対象なのでしょうか。あるいは、田園風景が広がる里山や近所の公園の森なども対象に加えるべきなのでしょうか。こうした根源的な問いについても、現実の法や政策の経緯と現状も踏まえつつ、正面から考えていきます。
本書の特色としては、「生物多様性と倫理、社会」を考える上で、「企業」と「NPO」の2つの視点から論じていることが挙げられます。なぜ、「企業」と「NPO」なのか。これは、一義的には、極めて単純な話として、筆者がこれまで深くかかわってきたアクター(主体)が企業とNPO(特定非営利活動法人という狭い意味ではなく、広く市民活動・市民運動を行うグループという広い意味で使います)であったからです。そして、それだけでなく、生物多様性の保全(あるいはその逆の自然破壊)に関係するアクターとしても、この両者は、良きにつけ悪しきにつけ、極めて重要な役割を果たしてきており、そうしたアクターやそれを取り巻く状況を探求することで、より具体的な生物多様性の保全のあり方を描くことができると考えたからにほかなりません。
読者の皆さんには、本書を読みながら、対象となる自然に思いを馳せ、自然や生きものについて興味をもち、それを好きになってくれる人が増え、ともにその抱える課題について考えていけることを願ってやみません。
なお、現在は、「気候危機」や「海洋プラスチック」など、急激に変化する生物多様性を巡る動向をも反映させた「改訂版」が発行されています。
【目次】
はじめに/改訂版の発行に当たって 第1章 「生物多様性」とは何か
第2章 企業と環境
第3章 企業と生物多様性
第4章 海の生物多様性と倫理、社会①-東京湾三番瀬の自然と開発
第5章 海の生物多様性と倫理、社会②-自然再生と市民参加
|
第6章 人と生物多様性①-生命倫理、環境倫理を考える
第7章 人と生物多様性②-人にとって保全すべき生物多様性とは
第8章 法と生物多様性①-人権と「自然の権利」
第9章 法と生物多様性②-環境法の進展と課題
おわりに |
◎十文字学園女子大学 教授・片居木 英人 先生
人間生活学部、人間福祉学科、2年生前期(半年)
『行政福祉総論・講義』(「はじめに」より抜粋・加筆)

本書を『行政福祉総論・講義』としたのは、「行政福祉」の基調に日本国憲法、とりわけ人権論を据え、地方自治論とも関連づけて展開していこうとする意欲と姿勢を示そうとしたからです。
もしかすると、皆さんの中には、初めから「公務員になる」という志望をもって、受講されている方もおられるかもしれません。しかし、改めてここで、「なぜ公務員をめざすのか」について考えてみましょう。「時間が定時(9時~17時)だから?」「給与が安定しているから?」「身分が安定しているから?」「休暇取得が確実だから?…」など≪安定しているから≫というイメージからの理由にはなっていませんか。
でも、実は公務員という職業はとても“怖い”ものなのです。
公務員は、権限を行使して-権力をもって-国民の(住民の)権利や自由に制限を加えることができる公的組織(私たちの税金で成り立ち運営される存在)の一員であり、その職にあり、その地位にある者なのです。公務員の行った行政行為は、根本的には、法律に照らされて、その行為の合法性、正当性、適正手続性、責任の所在が、日々問われることになるのです。そして、そうした公的組織への従事についての緊張感をもって、行政職としての職務に堪えられるかどうか、自己の適性を十分に分析・点検したうえで、公務員をめざすことが、強く求められるのです。
以上のことを確認したうえで、「行政福祉」を捉える視点や立場について明らかにしていきます。
第一は、一地域住民として、です。私たちは誰もが、その地域に暮らす住民として生き、生活しています。そして必ず、生存権確保のために、各種の行政福祉サービスを利用しています。決して「行政福祉」と無関係ではありません。一地域住民として(一市民として)、「行政福祉」と密接に関わっているのです。つまり、行政福祉サービスの内容や水準、利用手続の方法(アクセスのしやすさ、情報公開等)に意識を向ける必要があるということです。
第二は、一主権者(有権者)として、です。私たちは、一人ひとりが、国の政治(国政)に対しても地方政治に対しても、その政治のあり方を最終的に決定する力をもつ主権者です。特に18歳以上の者は、直接に政治に参画する(投票する権利を有する)有権者です。生存権のあり方を左右する「行政福祉」に無関心というわけにはいかない憲法的地位・立場にある、といっても過言ではありません。
第三は、地方公務員(国家公務員を含む。)を志望する者の一人として、です。先にも述べたように、公務員は、権限を行使して-権力をもって-国民(住民)の権 利や自由に制限を加えることができる公的組織-私たちの税金で成り立ち運営される存在-の一員であり、その職にあり、その地位にある者なのです。行政福祉総論を通して、行政や社会福祉、地方自治に関する基本的知識の理解や倫理観を形成し、人権尊重の意識を涵養し、自分ははたして行政職に向いているかどうかの適性を見極めていく契機とする必要があります。
皆さんそれぞれにとっての問題意識をもっていただき、「行政福祉総論・講義」を始めようと思います。
【目次】
|
はじめに 目 次 第1章 「行政福祉」を捉える視点-日本国憲法を基調として 1 憲法13条「個人としての尊重、生命権・自由権・幸福追求権の最大の尊重」 2 憲法14条「差別の禁止=平等権」 3 憲法25条「生存権とその保障における国家(自治体)責任の明確化」 行政の実務から① 第2章 「行政福祉」とは何か 1 広義としての意味 2 狭義としての意味 行政の実務から② 第3章 行政とは何か 1 行政とは 2 法律による行政 3 行政権力の位置づけ(三権分立) 4 権力とは何か 行政の実務から③ 第4章 行政権(力)の本質とは 1 権力の行使 2 裁量権の行使 3 官僚制としての行政機構 4 行政組織・機構のメリット、デメリット 5 公益通報者保護制度 行政の実務から④ 第5章 行政の活動 1 規制行政 2 給付行政 3 調達行政 4 権力的行政作用と非権力的行政作用 5 公共サービスとは-公共サービス基本法 行政の実務から⑤ 第6章 地方自治体とは何か 1 地方自治の本旨とは ⑴ 団体自治 ⑵ 住民自治 2 地方自治の捉え方 ⑴ 地方自治への歴史 ⑵ 地方自治をめぐる学説的見解 ⑶ 地方政府という考え方 行政の実務から⑥ 第7章 地方自治法が規定すること 1 地方自治体の目的 2 地方自治体の役割 3 国と地方自治体との関係 4 地方公共団体の区分・分類 ⑴ 普通地方公共団体 ⑵ 特別地方公共団体 ⑶ 基礎的団体と広域的団体 ⑷ 法人としての地方公共団体 行政の実務から⑦ 第8章 地方分権一括法の意味したこと 1 その時代的背景 2 機関委任事務の廃止 ⑴ 機関委任事務とは ⑵ 機関委任事務の廃止 3 法定受託事務と自治事務 ⑴ 法定受託事務 ⑵ 自治事務 行政の実務から⑧ 第9章 地方公共団体における「住民」 1 住民の意味及び権利義務 2 住民としての「法人」 3 住民の権利 その1(直接選挙権) 4 住民の権利 その2(直接請求権) ⑴ レファレンダム ⑵ イニシアティブ |
⑶ リコール ⑷ 議会の解散請求権 ⑸ 行財政についての監査請求権 ⑹ 行財政についての情報公開 5 住民の義務 行政の実務から⑨ 第10章 地方公共団体における公務員 1 その役割 ⑴ 市区町村の公務員 ⑵ 都道府県の公務員 ⑶ 国家公務員 2 公務員の法的性格 ⑴ 全体の奉仕者 ⑵ 公務員に求められる憲法尊重擁護義務 3 公務員の職務遂行に伴う義務 ⑴ 法令及び上司の職務上の命令に従う義務 ⑵ 職務に専念する義務 ⑶ 身分の保有に伴う義務 行政の実務から⑩ 第11章 自治立法権 1 地方自治体の条例・規則制定権 2 地方議会による条例制定権 3 自治基本条例の制定 4 百条委員会とは何か 行政の実務から⑪ 第12章 自治行政権 1 自治行政権とは 2 地方自治体の長としての団体統轄及び担任事務 3 内部組織 行政の実務から⑫ 第13章 自治財政権 1 地方自治体の財政 2 地方自治体の会計 3 地方財政法 4 予算の原則 ⑴ 予算の事前決議の原則 ⑵ 予算公開の原則 ⑶ 総計予算主義の原則 ⑷ 予算単一主義の原則 ⑸ 予算統一の原則 ⑹ 会計年度独立の原則 5 地方財政の財源と現状 行政の実務から⑬ 第14章 行政法からの「行政」の理解 1 行政行為とは 2 行政行為の効力 ⑴ 拘束力 ⑵ 公定力 ⑶ 不可変更力 ⑷ 自力執行力(執行力) ⑸ 不可争力(形式的確定力) 3 行政行為における行政裁量 ⑴ 羈束行為 ⑵ 裁量行為 4 瑕疵ある行政行為 ⑴ 無効な行政行為 ⑵ 取り消しうべき行政行為 5 行政指導 6 行政手続 ⑴ 処分 ⑵ 行政指導 ⑶ 届出 ⑷ 命令等 行政の実務から⑭ 資料 新座市自治憲章条例 参考文献 おわりに |
